14.03.10
ものがたり在宅塾2014 第6回 「何所で最期を迎えるのかを選べる地域文化の創成」
ものがたり在宅塾2014 第6回 2014/1/20

「何所で最期を迎えるのかを
選べる地域文化の創成」
佐藤伸彦氏
(医療法人社団ナラティブホーム理事長)
現在、在宅で亡くなる人の割合は10~15%。病院で亡くなる人が増えて在宅死を上回ったのが1976年(昭和51年)ごろ。わたしが18歳で富山に来たころ、富山西武が開業したころだ。そのころから死生観が議論されるようになった。ホスピスが注目されるようになったのもこのころ。
今後、医療機関や介護施設の病床数が増える予定はない。病院死が大半を占める今のままなら2040年には約50万人が容量をオーバーして亡くなる場所が見つからない。どこで看取るのかが課題になっている。 団塊の世代が65歳を超えていくと高齢化は急激に進む。ここ砺波市庄東地区の高齢化率は30%を超えており、市平均25.8%を上回っている。どう対応していくかは医療側だけではなく、みなさんとともに考えなければいけない問題だ。どうやって最後までこの地域で暮らすのか、を考えていきたい。
■どこで・誰と・どのようにして最期を迎えるのか選べる時代に
高齢者の爆発的な増加によるって多死社会が到来する。どこで・誰と・どのようにして最期を迎えるのか選べる時代にしなければいけない。このことを強く訴えている。介護をする家族の負担を考えると、在宅のほうが良いとは言い切れない。在宅には家族に介護力が必要になる。しかし、長く入院することもできず選択肢がない。患者にとって必要なのは医療なのか、介護なのか。必要とするところに応えるかたちがあるとよい。
老老の介護が増えている。夫婦だけではなく、最近は老いた子供が親の介護をするケースが多くなっている。生涯未婚率は2010年で男20.14%、女10.61%(50歳の時点で結婚をしていない率)にのぼる。将来、独身の高齢者を誰が介護をしていくのだろうか。
人は必ず死ぬ。そこをしっかり看取り、それぞれの生き方を完結させなければいけない。「命」と「いのち」の違いを念頭に置いている。生命体としての「命」と、生まれ育って人生をこう生きてきたという物語られる「いのち」の違いだ。どちらを大事にするのか。これからの医療はもう少し後者の「いのち」を大事にしていかなければならないと考えており、「ナラティブ(ものがたり)」を重視して活動している。
■「命」と「いのち」のバランス
この「命」と「いのち」のバランスをどうとっていくのか。末期の患者に対してどれだけ延命治療を行うのか、それともその人らしい最後を選ぶのか。人の決断は10:0の確信のもとに下されるわけではない。患者自身や家族もぎりぎりの選択をしている。どちらか迷って6:4ぐらいで下した決断かもしれない。どうバランスをとるのかは難しい。人の心の動きは変わりやすい。患者の意見は変わったとしても医師は斟酌する必要があると思う。
どこに落とし所をもっていくのか考える時に最近思うのは患者も医師も「お互いさま」であること。これはインフォームドコンセントだと思う。医師側の考え、家族の考えを出し合ったうえでバランスが図られ、落ち着きどころが定まっていくのがよい。医療は不確実性が高く、やってみなければ分からない部分を常にはらんでいる。双方の事情を分かったうえで納得できる医療ができるようになるのがよい。
胃ろうは単なる医療技術であり手段にすぎない。よって胃ろう自体の是非は問えない。手段と目的を混同してはいけない。技術をどんな目的のために使うかが問われる。これは人工呼吸器についても当てはまる。胃ろうで栄養を摂取している患者であっても、飲み込む力が残されているならば本人の満足感を考えて食べたいという希望をかなえてあげたい。食べたものを胃ろうから回収したこともある。
■「それなりの人生だった」と思ってもらえるように
 親の死にざまは子供(孫)にする最後の教育だと思う。体が冷たくなること、しゃべらなくなることなど五感をもって子供たちは死というものを知る。多くの人に来てもらって家族が看取る。スタッフは看取るのではなく、サポートするだけだ。やり残したことはないか/言い残したことはないか/食べ残したものはないか、を尋ねてできるかぎり対応してあげたい。
親の死にざまは子供(孫)にする最後の教育だと思う。体が冷たくなること、しゃべらなくなることなど五感をもって子供たちは死というものを知る。多くの人に来てもらって家族が看取る。スタッフは看取るのではなく、サポートするだけだ。やり残したことはないか/言い残したことはないか/食べ残したものはないか、を尋ねてできるかぎり対応してあげたい。
誰も死は経験できない。誰もがやり直すことのできない、一回限りの生をいきている。これを常に考えなければいけない。わたしはこのことを患者さんから教えてもらった。「平穏死」「満足死」などといった言葉があるが、良い死なのかどうかを問う必要はない。自分が死んだら分からない。所詮は残された者の考えで言っているだけだから。
死ぬ時に「いろいろあったけれど、それなりの人生だった」と思ってもらえるようにしたいと思う。
人は誰でも、他人に理解されないものを持っている。もっとはっきり云えば、人間は決して他の人間に理解されることはないのだ。親や子、良人と妻、どんなに親しい友達にでも、人間はつねに独りだ。(『樅ノ木は残った』山本周五郎)
この言葉をケアの原点としている。いかにも分かったようにふるまうのはおかしいと思うから。その人を理解する努力をすることから始まる。
「看取る」主体は医療者ではなく関係性のある家族である。わたしたちは看取りの支援者。さりげない第三者でありたい。「看取り」というよりも「死に寄り添う」という表現が合っているかもしれない。寄り添う距離感は人それぞれで違う。
死は点ではなく、奥行きも幅もある。時間の流れの中にあるのだと思う。死者として生まれ変わり、人の心の中で生きる。わたしの父も母もわたしの心の中にある。末期患者の家族に対するグリーフケアは死ぬ前から始まっているのではないかと思う。
物語的理解を大事にしている。頭で理解するというよりも、「あっそうだよね」と分かること。「腑におちる」という表現がふさわしいかもしれない。
生きざまは死にざまであり、人間は生きてきたようにしか死んで行けない。しかし人は変わることができ、最期まで希望を捨ててはいけないと考えて医療に当たっている。
死期の近い患者がわたしの仕事をねぎらってくれる。折り込みちらしの裏に死後の始末のような大事なことを書き記したりする。「人間は哀しい」が「弱さの強さ」をみる。その人は、最後までその人である。たとえ認知症になったとしても、そう思ってかかわっている。
■地域医療の究極は街づくり
地域医療は医師だけではできない。医療関係者の連携だけでもまだ狭い。ほかの職種の人、さらに地域住民と連携しなければできない。その中で医者は医療のことを担うのが理想。地域医療の充実を目指す活動は街づくりそのものといってもよい。住民のまちづくりにわたしたちも参加させていただく。医療をいかにうまくつかうかを考えていただきたい。
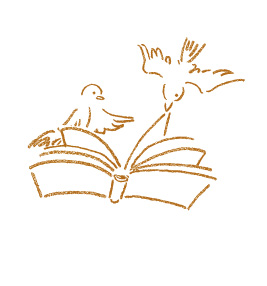 <ナラティブホーム>
<ナラティブホーム>
そこには人生の最終章を
家族と伴に
ゆっくりと、安心して過ごせる
空間がある
ただ傍らに在り、温もりを感じ
声なき声を聴け
ケアの原点は
心象の絆の中にある